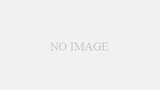教壇の工夫(問)
… 助松先生・米澤先生のお話 …
教壇の工夫が子どもを育てます。教材の中に子どもが溶け込んでいくといいましょうか、子どもの中に教材が溶け込んでいくといいましょうか。教材と子どもが一つになっていく工夫をするところに、教育が生まれていきます。この教壇の工夫が何とも楽しいものです。
(助松太三先生 S54年1月5,6日 山梨 上野原町立棡原小学校)
私が教式を学んでいなかったら、授業の工夫をする喜びを決して持たなかったと思います。考えるうちに、新たな発見や気づきが生まれ、子どもたちの顔が浮かんで、ますます楽しくなります。今は、スマホやパソコン等で簡単に情報が手に入ります。指導案等も、そのまま使って、授業ができるようです。AIが先生の代わりに授業する等ということも起こりうるかもしれません。それで、本当に子どもが育つのでしょうか。
芦田先生が米澤先生に「問」の秘訣を次のように話されたそうです。
「子どもの眼から自分の眼を離すな。問いをかけて、子どもの眼の中に少しでも色がちろっと動いたら、これは、自分の問いがおかしいのだ。変なことを聞いたのだと思いなさいよ」
米澤先生はこれを受けて、「『問』そのものが子どもに分かることが根本だ。『問』が子どもに浸透することが、一切の学習の根本だ」と、考えられました。
先達のご教壇の「問」の深さ、分かりやすさは、この信念によるものだと思います。自分の甘さを改めて考えるお話でした。うかうかと過ごした日々を悔いても取り戻すことはできません。でも、残された日々を大切に学んで行きたいなと思います。
島根 M.N