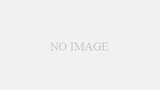観阿弥と先達の姿
世阿弥の父観阿弥は、1384年5月、52歳で死去しました。その月の初めに、駿河の浅間神社で法楽を行い、人々に大きな感動を与えたのです。その頃の観阿弥は、大部分の演目を若い人に任せていました。
「これ、誠に得たりし花なるが故に、能は枝葉も(少なく)老木になるまで、花は散らず残りしなり。これ、目のあたり、老骨に残りし花の証拠なり。」
この観阿弥の姿は、70歳を過ぎても壇に立ち、後進に教式の道を伝えて下さった先達の姿に重なります。常に自分を振り返り、次に生かす工夫をされる姿を通して、私たちは学び続けることの尊さ、厳しさを教わりました。
その中でも、倉員先生は早くから教壇を若い人たちに譲り、裏方に徹していずみ会を支えて下さいました。壇に立たれなくても、色々な場で助言を下さいました。
「教壇に立てなくても淋しくはない。日々の生活の中に教壇がある。」と話される先生は、「生活即教壇」が信念でした。
今は教式の実践も難しくなっていますが、しかし、教式を七変化の形式だけでとらえるのではなく”どの子も育つ”という、芦田先生以来脈々と受け継がれてきた「教式の心」を護っていきたいと考えています。
*法楽…神仏に奉納し、神慮・佛意を慰め奉る能
島根 M. N