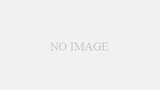ので、から文
『助詞・助動詞の辞典』を読んで、長年の疑問が解けた。それは、2・3年生の作文の「ので、から文」についてである。
「ので、から文」というのは、「ので、から」を使って文を続けるところから出た言葉で、そんな作品に朱を入れると、真っ赤になってしまう。でも、担任は、そんな作文を丁寧に読んで、作者の書かんとする心情を汲み取り、思う存分に書かせることが大事である。文を切って書くことを強要する朱を入れるのはよくない。朱を入れるのではなく、読みの学習を丁寧に扱いながら、作文にも活用していくようにするのがよいというのである。実に、穏やかな作文の指導法である。
と、私は教えられた。
辞典の一部を記すと、
二つの叙述をただ繋げているのではなく、これから述べる後件内容の前提として、前件がどのような関係にあるか、話者の認識判断がこれら接続をつかさどる助詞として現れている。その点では、「しかし」や「だから」などの条件接続詞と共通の機能を担っているわけだが、いったん文を切って、改めてそれに対する判断を加える接続詞の論理性寄りにくらべ、先行叙述内容への話者の心的態度を表す流れの中で、次に述べようとする事柄へと移行していく過程として、後続叙述が導かれる話者の意識内容を接続助詞の形で言葉に表す。前件・後件の叙述内容間の論理的関係を示すというよりは、先行叙述を打ち切ることなく感情の流れに乗って、さらに話を展開させていく”表現意識の連続性”といった情的な面の濃い表現方式である。
と、なっている。
この「情的な面の濃い表現方式である」に気づいたのである。「ので、から文」というのは、子どもの心情が素直に出た文章なわけである。
ところで、読み手に分かり易い作文を書くということは、客観的に見る力が必要である。でも、「ので、から文」を書いている子どもたちには、まだその力がついていないのであるが、書かんとするエネルギーは大きなものがある。
そのエネルギーをからすような指導は、今は控えることだったんだと、先達の教えが納得できたのである。
東京 T.K