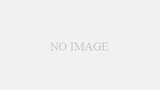よかったね。
いずみ会の教壇修養会では、
「『よかったね。』の中に、喜んでいる気持ちが強く出ている字があるが、どれか分かるか?」など
丁寧な語感の扱いをする教壇に出会います。
「よかったね。」だけ抜き出したのでは、いろいろな感じ方が出てくると思います。LINEに「よかったね。」と送られてきた場合と電話で聞いた場合では、どちらの方が相手の気持ちが分かるでしょうか。また、立ち話をしている場合なら如何でしょうか。
ここに、国語の読みの指導の注意点が、潜んでいます。
以下は、本の帯に惹かれて購入した『助詞・助動詞の辞典』<森田良行著 東京堂出版>からの抜き書きです。 プロローグ p19より
いずれにしても、これら「助詞」と言われる一群の語彙は、表現形式を視野に置くか置かないかは別として、表現内容を形成するにあたって、話者の認識判断の味付けを加えていく重要な働きをしている。その点、英語など単に事柄の内容をドライに叙述するだけの言葉とは大いに性格を異にしているわけである。確かに、事柄と事柄との関係や有り様を直截的に言葉に乗せる方式は、一見論理的に見える。日本語に見るように、話者の主観的な認識の有り様や心理に根ざす語彙をその都度添えていく言語は、はなはだ情的で論理性軽視の言語のように見えるかもしれない。しかし、それは誤解であって、叙述内容そのものは間違いなく状況を正確かつ論理を曲げることなく伝えている。その上、話者のそれに対する把握認識の有り様までも加味されているのであるから、論理と感情の両面を合わせ持つ性格の言語と見てよいだろう。その長所を正しく認識して、上手に駆使することこそ、日本語話者の特権であり義務であると思うのである。
と、日本語の特徴を示しています。これは、小学校教師の基礎的な知識になっていなくてはならないことだと、認識を新たにしました。
東京 T.K