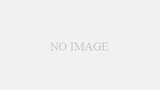未 見 の 師、鈴 木 佑 治 先 生
「いずみ会」の創始者である鈴木佑治先生のお名前を知ったのは、いずみ会に入ってからのことであった。芦田先生の孫の倉員富美子先生より、
「『鈴木先生は、カラスの鳴かぬ日はあっても、私が、芦田先生を思わぬ日はないのです』
という先生でありました。そして、芦田先生の【 正 風 護 持 】に徹底した先生でありました」
と、教えられた。
芦田先生の「七変化」の教式は、
一、読む
二、話し合い
三、読む(教師)
四、書く
五、読む(板書事項)
六、わけ
七、読む
(「教式」の記述は、『国語教育易行道』「教式」からの引用である)
となっているが、中でも三の教師読みは、「着 語」というものを入れた芦田先生独特のもので、教師中心と、戦後批判された。
鈴木先生は、考え抜かれた末、誰もが指導出来るように、「児 童 中 心」になるようにと、三に「手引き」を開発され、「師 弟 共 流」の国語教育を指導して下さった。この手引きにより「いずみ会」では、道友が平易に授業ができるようになり、今日に及んでいる。
鈴木先生には直接ご指導をお受けすることが出来なかったが、その「学 恩」に感謝し、「居ますが如く」未見の師を想う次第である。
担当 京都 A.T
*注 鈴木先生の国語科指導の単純形態では、七変化の教式を以下のように示している。
一、よむ 二、とく 三、よむ 四、かく 五、よむ 六、とく 七、よむ
手引きは、〈三、よむ(黙読) 四、かく(視写)〉の前、
二、とく ○題目 ◎ひびき ○手引き(第一次)
同 ○おさらい ◎承接 ○手引き(第二・三次)
と位置付けられている。