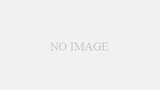芦田先生の「小学国語読本と教壇」より その1
教壇へ ここが教師の働くべき真の天地だ。いくら深く学理を研究しても、これを教壇へという工夫と努力と修行がなかったら、学者としては尊くても、教育者ではない。教育者の磨いても磨かなければならない所は教壇だ。
全集第15巻 P.380
教材研究なしに授業をすることはできません。また、その研究成果を授業に具現化できなければ、教師の仕事は成立しません。そのために「工夫と努力と修行」が求められるのですが、私はその見通しすら立てられず、闇雲に調べてそれを児童に解説したり、字面をなぞって終わるような授業をしていました。
それを乗り越えられたのは、いずみ会の教式のおかげでした。
「教式は、教材研究と立案と指導の三者を同時に成立させる」
(笠原昭司先生)
「地上一粍の向上と口先では言いますが、一粍の向上とは並大抵のことではありません。何年努力しても、一粍にならないことがあります。ところが行ずる者の世界には、あるところにいくと飛躍する力が生まれることがあります。これこそ行ずる者の強みであると思います。飛躍に飛躍を重ねていくには、「理」をやめて「行」を専門にしていくことです。(鈴木佑治先生)
修行は、どこまで行っても長い道。
※「小学国語読本」は、昭和8年4月から使われ始めた国定教科書です。芦田先生が、その全教材の取扱いをお書きになったのが「小学国語読本と教壇」で、芦田恵之助全集では第15巻から第21巻に掲載されています。教材を「読む」ということに目を開かせてもらえます。未読の方は是非ご覧ください。
岩手 Masa.K