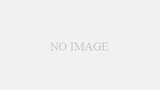いずみ会に学んで
いずみ会を知ったのは、教員になって3年目、転勤した学校で東京いずみ会に参加している先生と出会ったからです。
当時、東京いずみ会は毎月第2土曜日、学期末のみ第1土曜日に開かれ、教材実習と授業の会がありました。指導者は、助柗太三先生と杉田すま先生、司会が倉員富美子先生で参加者も大勢いました。七変化の教式を学び「子どもに理会(とっぷりわかる)させていく営みが教壇である。」と教えていただきました。
4月は1年生入門期の教式で、1年生を担任している先生の報告でした。その頃、2年続けて1年生の担任だった私は、この教式が役立ちました。指導書に頼らず、自分で考え立案し、ノートに書いて授業する大切さを学びました。
作文指導も教式で学び、批正の授業を市内の国語同好会で公開し、子ども達の聴写の力が認められたのは、嬉しいことでした。
国語教壇修養会の授業は、どれも忘れられません。どの先生の授業も、その場面が思い浮かびます。特に初めて参加した修養会、1年生「月夜のからす」の楽しく迫力のある授業に引き込まれ、記録する手が止まっていました。暗誦、暗写までした米澤先生に敬服でした。教材を書いてみることの大切さを学びました。
助柗先生は、いつも考えたり、工夫したりするのが楽しいとおっしゃっていました。私もいずみ会で学んで、国語の授業が楽しいと思えるようになりました。
ひたすらに 心を読み考え 心を表す
53年秋 助柗
と揮毫した色紙の額をいただき、今も私の部屋に掲げています。
これからも「尊きは日々の生活なり」「共に育ちましょう」と教えていただいたいずみ会に参加したいと思います。
東京いずみ会 N.N