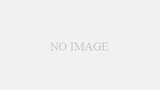…… 小学校の国語の授業を考える ……
「かさこじぞう」(その1) ~ 23年温めた教壇 ~
明けましておめでとうございます。
お正月にふさわしい教材と言えば「かさこじぞう」です。
そこで、今月は、「かさこじぞう」に関わる話題を取り上げます。
昭和63年1月の国語教壇修養会で、いずみ会の先達である笠原昭司先生は、「かさこじぞう」を扱われました。
当時校長をされていた、宮城県古川市立宮沢小学校における第95回国語教壇修養会での授業でした。
これは、笠原先生が現職として教壇に立たれた最後の授業であり、授業されての感想を、修養会の筆録に次のように書かれておられます。
「かさこじぞう」は、私のあこがれの教材でした。
鈴木先生が、「かさこじぞう」を扱って下さったのは、昭和39年の冬の会でした。
(中略)いつの日か、
「かさこじぞう」の教壇をいずみ会で行じてみたいと、その時から思っていました。
笠原先生の師、鈴木佑治先生の「かさこじぞう」の教壇をご覧になって以来、約23年もの間、温めてこられた教壇でした。
このとき、指導部長米澤德一先生は、「悠々たる境地を開かれた教壇。」と評されました。
さらに、
「子どもに密着している。民話の語り口が出ている。幼稚園での語り(注)が年と共に熟してきた。無駄がない。必要のないことはやらない。」
と激賞されています。
注:隣接する幼稚園長を兼務され、毎日読み聞かせをされていた。
鈴木佑治先生が取り扱われたのは、3年の教材で、「かさじぞう」という題目でした。
「正月には、もちの一つも食べたいものだが、売る品物もないし……。」
笠原先生の授業は、現在と同じ2年の教材で、挿し絵は違いますが文章は同じです。
「ああ、そのへんまでお正月さんがござらっしゃるというに、もちこのよういもできんのう。」
じいさまの言葉の違いが、授業の構想に大きく影響を与えています。
これは、次回の話題にします。
なお、1月4日は、笠原先生の命日です。
(笠原昭司先生は、平成18年1月4日享年80歳で逝去されました。)