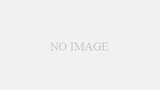…… 小学校の国語の授業を考える ……
「かさこじぞう」 (その2) ~ お正月様とお地蔵様 ~
鈴木先生の「かさじぞう」は、おじいさん、おばあさんのお地蔵様に対する敬愛の心と、貧しくとも安心して生きる清貧の心を見事に具体化したものでした。
(第95回国語教壇修養会 笠原昭司先生の感想文)
具体化の例 ( 第二次指導 二と く◎足場 《現在の〝承接〟》 )
〇 おじいさんは家を出る時は、自分の口を考えたの。
あしたは、この笠を売ってもちにして、と思って売りに行ったのだろう。
ところが、みんな、お地蔵様にただであげたのだよ。
〇 おじいさんは、お地蔵さんの前に来たときは自分の口を考えたのか。
考えない。
〇 誰のこと考えたの。
お地蔵さん。
〇 お地蔵さんのことです。……雪をいっぱいかぶって、お地蔵さんは立ってござる。
かわいそうだなあと思ったの。もう、自分のかわいそうなのは、すっかり忘れたの。
この部分に触れて、笠原先生は、
「おじいさんは、きっと、若い頃に亡くした子どもの姿を、雪まみれのお地蔵様のお姿に見出した
のではないかと思います。『かわいそうだなあ』と思う気持ちには、そんな心がこもっているの
だろうと思いました。」
と書いておられます。 (第48回国語教壇修養会 笠原先生の感想文)
笠原先生の「かさこじぞう」は、鈴木先生のお取扱いを踏まえつつ、お正月様の来訪を明確に意識されたご教壇でした。これは、前回申し上げたように、教材文の違いに起因するものです。
笠原先生は「かさこじぞう」の取扱いについて、次のように書いておられます。
〇「かさこじぞう」の文章構成
「かさこじぞう」は、二つの話題によって構成されています。
それは、
⑴ お正月を迎えるという歳取りの用意
⑵ 地蔵信仰
の二つです。
⑴の方では、歳取りの用意、正月の買い物、という楽しく、忙しい行事です。…(中略)…
犬も猫も手伝ったという昔話はたくさんあります。…(中略)… 歳取りの昔話は数えきれません。
貧しい東北にとっては、歳取りと正月は年に一度の楽しみなのです。
⑵の方は、昔話の中に
「六人産んで六人死んだ。六地蔵様になったからもう死なないと思ったら二人また死んだ……」
というのがあります。
笠こ地蔵の話と重ねて考えると、
雪に埋もれて立っている地蔵様は、そのまま、あの世へいった我が子でなかったのか
と思われてなりません。
寒かろう、笠をかぶせてやろう、と思う心は、地蔵信仰よりももっと身近な情愛であろう
とも思われるのです。
この二つの昔話が一つになった美しい話が「かさこじぞう」であると思います。
これを、「善根を積めば幸福が来る」などという図式でよみとってはならないと思います。
この話の構成は
⒈ お正月様を迎えるために買物に行く
⒉ お地蔵様に笠をかぶせてあげる
⒊ もちつきのまねごとをしてお正月様を迎える
⒋ お地蔵様がお正月様を迎えるための物をもってきてくださる
と四つになります。
第二次指導では、どうしても、⒉と⒋に重点をおいて扱いたくなりますが、⒉と⒋だけを扱うと、
単なる「地蔵の恩返し」になってしまいます。⒊をからませないと昔話の味がでてきません。
(笠原昭司著「教式の話」54・55頁)
鈴木先生は、お地蔵様への「敬愛の心」を深く取り扱われました。その印象は、直後に書かれた笠原先生の感想文に書かれており、それが「教式の話」の地蔵信仰の文章にも引き続いていることが分かります。教材文の変化に合わせて、「お正月様」への篤い信仰がつけ加えられたのが、笠原先生の「かさこじぞう」のご教壇だと思います。
次回は、笠原先生の「かさこじぞう」のご教壇を紹介します。