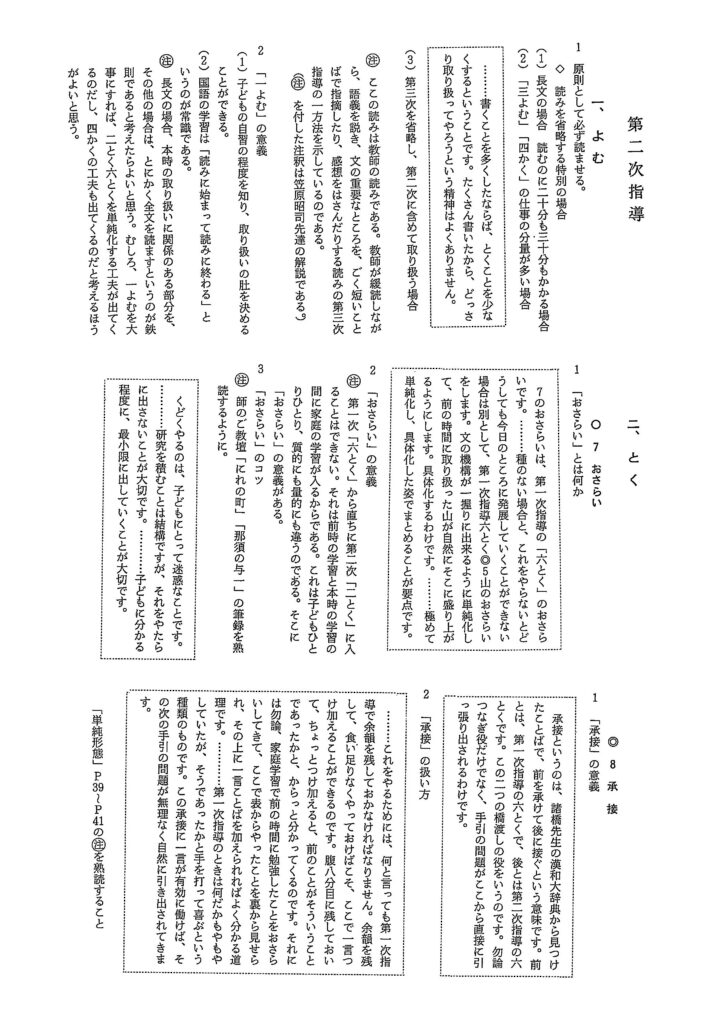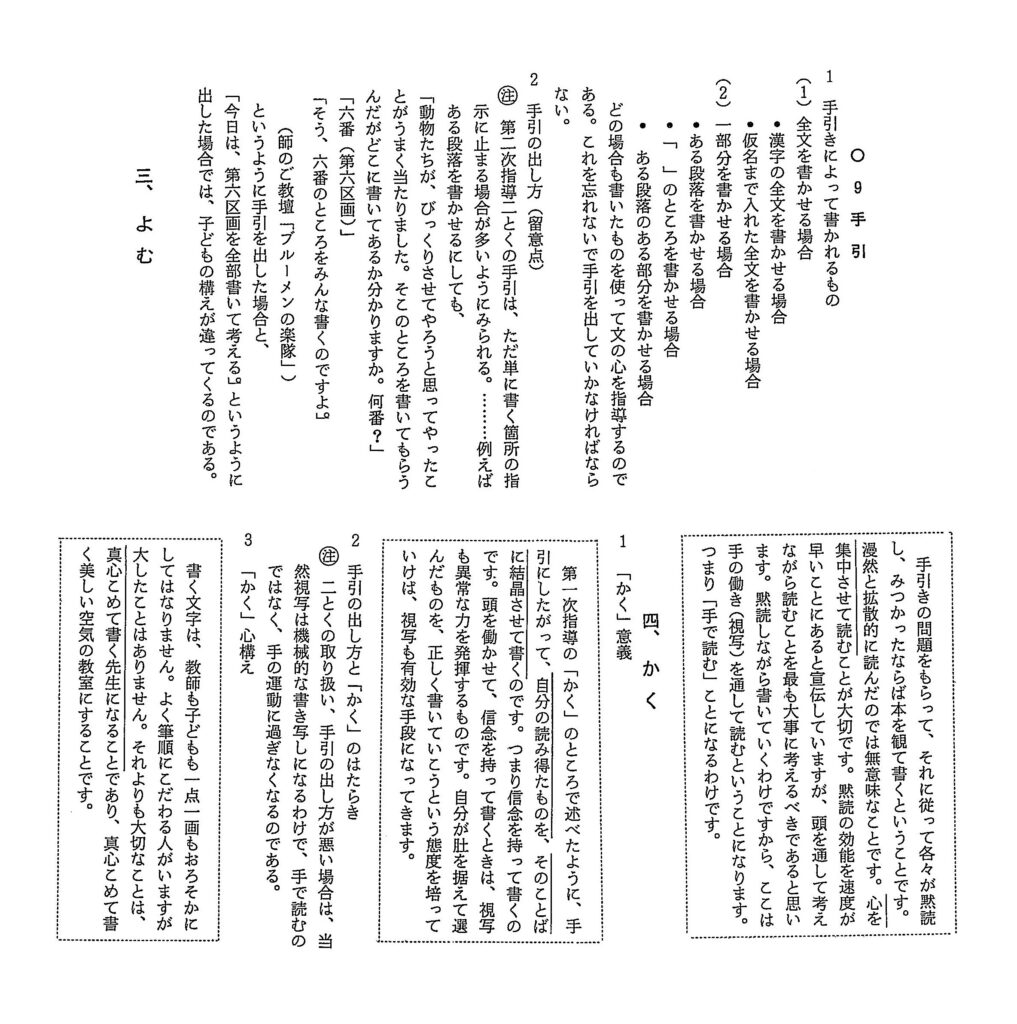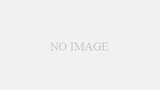…… 小学校の国語の授業を考える ……
国語科指導の単純形態を求めて ⑤
いずみ会百回記念誌 (平成3年3月刊)
先週はリモート研究会(9月例会)を受けて作文指導でしたが、今週は第23週の続きです。佐々木秀也先生の教式の話:第二次指導:です。
第二次指導 ( 一よむ 二とく 三よむ 四かく 五よむ 六とく 七よむ )を3回に分けて載せます。今回は ⇒ 「一 よ む」 ~ 「四 か く」 です。
一、よむ
1 原則として必ず読ませる。
2 「一よむ」の意義
(1) 子どもの自習の程度を知り、取り扱いの肚を決めることができる。
(2) 国語の学習は「読みに始まって読みに終わる」というのが常識である。
二、とく
〇 7 おさらい
1 「おさらい」とは何か
2 「おさらい」の意義
注 第一次「六とく」から直ちに第二次「二とく」に入ることはできない。それは前時の学習と本時の学習の間に家庭の学習が入るからである。これは子どもひとりひとり、質的にも量的にも違うからである。そこに「おさらい」の意義がある。
3 「おさらい」のコツ
◎ 8 承接
1 「承接」の意義
2 「承接」の扱い方
〇 9 手引
1 手引によって書かれるもの
(1) 全文を書かせる場合
・ 漢字の全てを書かせる場合
・ 仮名まで入れた全文を書かせる場合
(2) 一部分を書かせる場合
・ ある段落を書かせる場合
・ 「 」のところを書かせる場合
・ ある段落のある部分を書かせる場合
どの場合も書いたものを使って文の心を指導するのである。これを忘れないで手引を出していかなければならない。
2 手引の出し方(留意点)
注 第二次指導二とくの手引きは、ただ単に書く箇所の指示に止まる場合が多いように見られる。……詳しくは下記を
三、よむ
四、かく
1 「かく」意義
2 手引の出し方と「かく」のはたらき
注 二とくの取り扱い、手引の出し方が悪い場合は、当然視写は機械的な書き写しになるわけで、手で読むのではなく、手の運動に過ぎなくなるのである。
3 「かく」心構え
詳しくはこちらへ (p354~359) 下記へ